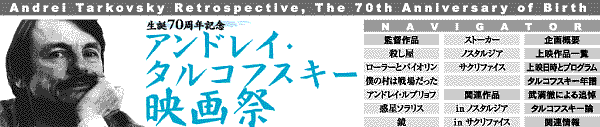
 『アンドレイ・ルブリョフ』(1967)撮影中のタルコフスキーとルブリョフ役のアナトーリー・ソロニーツィン 『鏡』(1975)製作中のタルコフスキー 『ストーカー』(1979)のセットで役者たちとともに
『サクリファイス』(1986)の撮影中の合間、役者の子供と |

───咋年(1986年)の暮、12月28日にタルコフスキーが、パリで亡くなりました。ガンだっだんですが、訃報をお聞きになって、まずどんな風に思われました? 武満 ショックだったですねぇ。ここのところ映画人が相次いで随分亡くなっているけれど、僕はタルコフスキーの映画をとても身近に感じていたので打撃が大きかった。彼の映画ほど音楽的な映画はないと思ってました。とても好きでした。僕はあの人ほど偉くはないけれど、それでも自分の芸術家としての資質が彼に近いという感じを持っていました。『アンドレイ・ルブリョフ』を見た頃から一貫して、そう思っていた。随分たくさんのタルコフスキーの映画を観たような気がするんだけど、たった8本なのね。10本にも満たない。 しかし、彼は充分、映画で可能な仕事を為し了えたという感じがして──もちろん彼自身はもっと撮りだいものもあったでしょうけれど、僕ら観る側としては、充ち足りたタルコフスキー体験を味わったと思うんです。それはもちろん、もっともっと彼の作品を観たかったけれど、満足はしているという意味ですよ。 ───『サクリファイス』が遺作になってしまいましたけど、ちょうど『サクリファイス』の最初の試写があった、そのすぐあとでしたね。 武満 そう、『サクリファイス』を観て、翌々日でした。『サクリファイス』を観て、タルコフスキーによって満たされていたから、新聞を見てびっくりしましたね。ただ、『サクリファイス』を観終わって、なんか思いつめてるな、というか“死”を感じたんですね。あの人の映画には必ず“死”の問題が出てくるわけですけど、それにしても重い。ある種の絶対性というか、言葉を差し挟めないという感じがしたの。いつもならば観終わって川喜多和子さん(フランス映画社)に「素晴らしかったよ!」とか「これはお客が入るよ」とか、いろいろ余計な感想を言うんだけど、あの日だけは「う-む」と言ったきりだったのね。重い。映画が重ったるいということではなく、あそこまで思いつめているのかという重さね。芸術家の避けられない宿命というか、宇宙論的な同義反復を背負って、みんなに代わって贖罪する、そういったタイプの芸術家としては、最後に属する人なんでしょうね。 ことに今度の映画では、映画の前にバッハのマタイ受難曲(パッション)が流れるでしょ。あれはマタイの中でも最も重要なものです。ペテロがキリストを裏切って、鶏が三度鳴いて、そのあとで号泣するところに流れる音楽なんですね。神よ、憐れんで下さい、私の涙にかけて、と──。激しく許しを乞う歌なんです。あの曲が冒頭に出てきた。ドキッとしましだね。『ストーカー』や『惑星ソラリス』にあったようなある種の企図された文明批評といったようなものを、はるかに超えちゃったなということを直感しました。彼がマタイのあの曲を選んだということには、大きな意味合いがあったろうと思いますね。これはごく私的なことですが、僕は新しい作品を書くときに、いつもバッハのマタイ受難曲を聴いてから取りかかるんです。一種禊(みそぎフような──。ですから、あれを聴いて単なるタイトル音楽としてだけのものとは思えなかった。彼が映画の中で提示しているさまざまな事柄を、比喩的に解いてもしょうがないという気がしたんですね。例えぱ『ノスタルジア』では、ベートーベンの第九が出てきたり、焼身自殺があったり、それに例によって水も充分でしたし、いろいろな象徴にはこと欠かないわけで、それをキーワードに観るようなところがあったんですけど、今度の『サクリファイス』はそうした要素があまり目立たないし、またそうした見方はあまり意味がないんじゃないかという気がしました。 ───タルコフスキー自身、自分の死を予感して『サクリファイス』を作ったとお感じになりますか。 武満 感じました。というのも、彼の痼疾について知っていたし、そのことが常に気がかりでしたからね。 ───遺言的な内容だと。 武満 ええ。ただ、それにしては未だ生臭いほどの激しさもありますよね。自分自身をも含めて人間の罪を激しく糾弾している。バッハの使い方を見てもそれは分かるし、西欧文明がもたらした間違いに対しても、とても強く抗議していますから──。
───『サクリファイス』を観て感じたのは、“祖国”というものに対しての考え方なんですが、タルコフスキーの“祖国”は単に故郷として現われる祖国ではなくて、もっと大きな景色というか、独特な観念として存在しているんじやないか、そんなふうに思ったんですが。 武満 そうですね。非常に大きな祖国、という感じ。それは、例えぱ、フランスの作家ル・クレジオが書いているような、“地上において競い合う固有の生が旅立つ遥かな祖国”、という祖国なんですね。だから、具体的なロシアのどこそこということではなく、“人間の祖国”というものでしょうが、しかもそれはまた同時に、彼にとってそれはロシア以外の何ものでもないような祖国でしょう。彼の強い希求にも関わらず、それは、もしかしたら、ありえないものかもしれないし、あるいはほとんど失われてしまったものなのかもしれないけれど、どこかにあるんだという希求ですよね。 ───武満さんはタルコフスキーの全作品の中で何が一番お好きですか。 武満 僕は『ノスタルジア』が好きです。『ノスタルジア』も、やはり暗い作品だったんですけど、今度ほど息が詰まるようなところはなくて、もっと楽しめたんですね。 それから映画技術的な意味でも、いろんな発明が『ノスタルジア』にはあったと思うんです。たとえば、ドメニコが住む水に満たされた廃屋がありましたね。あの時の水音の録音には、びっくりしました。画期的な技術だと思った。彼の映画で僕が面白いと思っているのは、ある一つの場所(空間)の中で時間が動く──もちろん長回しをしていれば、日常的な時間も当然物理的に経過しますが──。そんなことではなくて、時間がいろんな顔をして、どんどん変質しながら動いていくのが分かるんです。モンタージュとか切り返しのショットでつなぐといった方法を一切とらずに、本当にそこに漂っている時間、動いている時間というものを、モンタージュ以上の効果をあげて表現している。それを助けているが音なんですね。音の使い方。彼自身、ブレッソンの音の使い方なんかをたいへん尊敬し気に入っていたようですけれど、タルコフスキーはブレッソン以上に音について細やかな神経を持っていますね。で、あの廃屋のシーンでどういう録音の仕方をしたのか不思議に思って、二度ほど見たんです。どうも、音を手前から奥へ、奥から手前へ移動させているんですね。そう考えるしかない。それをぜひタルコフスキーに確めたかった。音の移動で、固定画像の空間の質が有機的な質的変化をみせる。 そうしたことだけでなく、『ノスタルジア』の場合には随所に映画的に興味深いところがありました。主人公がホテルの部屋にいるときの時間経過とか、水音とか、難しい描写を、実によくあれだけ精細に、完璧にやった。ただただ感心しますね。 近ごろ人間の音に対する感性は、鈍ってきていて、とくに映画の場合、音が大きくなってきたということもあるんですけど、無神経になってきている。かならずしもドルビー・システムが悪いわけじゃないけどね。その無神経さと、タルコフスキーの感性は、対極にある。映画が音を手にしたときは、人間みな音に対してある驚きをもって、無垢な態度で、その音を聞き出そうとしたと思うんです。それがいつか機械の方が先に進んだために、人間が聞き出さなくてばいけない音を、機械に任せきりにしてしまった。人間の感性というフィルターを通さずにね。 ───退化していってるんでしょうか。 武満 退化していると言ってもいいでしょうね。技術は進歩して、昔だったら到底再生できないような音まで、フィルムで出せるようになっているけど、残念ながら、それと同時に人間の感性は鈍くなってきている。その中で、ブレッソンやタルコフスキー、『情事』を撮っていた頃のアントニオー二といった人たちは、素晴らしい感受性を持っていた。本当にタルコフスキーは最後までみずみずしい耳を持っていた。彼は音楽家になりたかったようですね。 ───そうらしいですね。 武満 でも、音楽家が必ずしも、耳がいいわけではなく、大半は耳の悪い人がやっている(笑)。僕が映画を好きなのは、映画は音楽だ、と思っているからなんです。タルコフスキーの映画には音楽が少ない。これは一貫してるんだけど、それは彼の映画が音楽的だからなのであって、ことさら音楽が入る意味がないんだろうと思うんです。限りなく音楽というものに近づこうとしている映画だ。まあ、こんなこと言うと、僕自身音楽家なんで、思い上がっているようにとれるかもしれませんが、でも、音楽という芸術が、言葉では説明できない、あるいは、言葉では補えないような思想感情を表わそうとしているものだとすれば、タルコフスキーも、映画という方法を通してそのことをいつも追求していたと思うんです。 もちろん音楽を楽しむということに限って言え」ば、娯楽としてだけ楽しめる音楽というものはいっぱいあるけれど、映画を通じて問題を追求している芸術家タイプの映画作家までが、音や音楽に対しては、かなり鈍感になっている。だから、そういう時代にタルコフスキーの音に対する感性は際立ってユニークでしたよね。 さっき宇宙論的な同義反復ということを言ったんだけれど、いつも彼の映画には水が出てくる。そしてその水はいつも何かを映している。映画が水を写して、その水に何かが映っている。つまり、その映画自体が映っている。そういう反復ですね。それはこの生まれたり死んだり、ということと同じことです。それにしても、惜しい人が亡くなったもんだと思いますね。大きな損失ですよね。彼の残した仕事が、これから僕らにとって役立つ方向にいけばいいと思うけど──。分からないですね。
──ソビエト、というとちょっと違う感じがしますが、最後までロシア人的な感じがありましたね。彼のような映画作家は、アメリカやヨーロッパからは出ないと思うんですね。 武満 そうですね。ソビエト独自な作家というイメージはすごくありますね。 ───ベルイマンなんかと較べられることがありますけど──。 武満 ええ。彼らのペシミズムが同質のものとして言われたりすることがあるんだけど、それは全く違うと思うんですね。ベルイマンは確かにペシミストだけれど、タルコフスキ-はペシミストではないと思うんですね。“水”にしても、そのイメージが非常に終末論的なイメージを伝えるけれど、同時につねに、始源の感情というものを伝えている。彼はベルイマンに較べてはるかに詩人なんでしょうね。だから人間の真実をどういうふうに見るかということでは科学的なわけで、宗教から政治まで全て入ってくるわけですよ。 そうですね。確かにソビエトからでなければ、タルコフスキーのような人は出そうもないですね。とてつもないスケールと、とてつもない繊細さ、この両方を持っていた。ソビエトのフィギィア・スケートの選手と、アメリカやヨーロッパの選手とそのスケールがかなり違うでしょ。そういう違いがありますね。ソビエトには、素晴らしい芸術的な風土があるんでしょうね。 『アンドレイ・ルブリョフ』なんかを作ったというのは、やはり、小さな意味での“祖国”へ生まれ、身を置いて育った祖国に対する念いが、そこにとても強くあったからだと思うんですね。ただ彼の偉さはそこに留まらなかったということです。つまり、国境線で仕切られる国を超えた。国境線を超えられる芸術というのは、多分、これからは映画をおいてしかないと思います。音楽ですらそれは無理かもしれないんです。 ───一見、音楽の方が国境を超えられるような気がしますが──。 武満 音楽では観念を表わせないけれど、映像では純粋な観念を表わすことができますから。 ───今後、タルコフスキーのような作家はなかなか出ないでしょうね。 武満 映画が、一面、かなり個人的なものになってきて、誰もが映画を作るチャンスが増えてきた。実際、ジム・ジャームッシュなんか極めて個人的な映画の作り方をしている。しかし、タルコフスキーのように、今日までの芸術的な伝統といったものの延長線上にあって、そのスケールが大きく、しかも新しい価値を生み出すというような作家はそう多く出てこないんじゃないか、という気がします。映画は商業主義と結びついていて、そのこと自体が悪い訳じゃないけれど、いまのところそっちの方の力が俄然優勢ですから、職人的に巧い作家は今後もどんどん出てくるでしょう。でも、タルコフスキーほどの、終始、一貫して詩と真実を追求するというような作家は、そうは出てこないでしょう。長い時間をかけて培われた映画言語を、あれだけ消化して、なおかつ独自な言語を作り出し、それが普遍性を勝ち得るというようなケースはそうやたら出てくるもんじゃないと思いますよ。しかもタルコフスキーの場合、それである程度、興行的にも成功していたというのは立派なもんですね。 以前、クリス・マルケルから聞いたんだけど、タルコフスキーがイギリスでオベラの演出をしたんだそうです。ムソルグスキーの『ボリス・ゴドノフ』を。それはとても素晴らしかったそうです。やはり舞台の上でも霧をたいて──。オペラであれほど見事な演出は、生涯観たことがないと言っていました。クリスは音楽にも詳しいし、よく観てる人だから、それは良かったに違いないと思いますね。
───タルコフスキーは、音楽にしても、美術にしても、文学にしても、総合的にすぐれた知識と感受性を持った作家だった、と言えば当り前みたいですけど──。 武満 もちろん、そうですね。その上で、これは誰もが言っていることですけど、言葉では表わせないもの、言葉では捉えられないもの、それを見出す手段としての映画だったんでしょうね。僕が彼の映画に打たれるのもそのことなんで、それで彼の映画は音楽的だ、なんて言うわけだけど、それももちろん、必ずしも正確なつかまえ方じゃない。でも、なにしろ、彼の映画を観終わった時は、良い音楽を聴いたあとのような気分になるんですね。『ノスタルジア』なんかは、ほんとうに満たされた。惚れちゃったという感じでしたね。ラストの、トスカーナの古い大聖堂の廃虚に小さなロシアの家があり、ズームで引いていく快感、まさに大スペクタクルでしたね。ああいうものは映画でしか実現されないものでしょ。 ───雪が降り出してね。 武満 そう、あれは凄かったな。彼は言い知れぬヴィジョンを持っていて、しかもそのヴィジョンは他人に見せたいというものではなくて、何よりも自分が見たいんですよね。そこが彼の素晴らしい芸術家たるゆえんでしょうね。人に見せることが巧い映画監督は、いっぱいいますからね。例えぱジュリアン・デュヴィヴィエなんかそうですね。だけど、自分は何を見ているのかよく分からないという感じです。つまり、タルコフスキーは、内的な衝動に非常に潔癖で、純粋で、エゴイストだった。それが僕らを感動させるんですね。僕たちは、いまなんとなく他人の顔を気にして生きていく状況に置かれている。それがソビエトだとさらにそのスケールも大きいわけですね。日本では、まあ他人の顔を気にしているとは言っても、せいぜい上司や親の顔を気にしている程度のなまぬるさなんでしょうね。そのために、厳しく自分を凝視(みつめ)る監督は、日本ではごくわずかしかいない。 タルコフスキーの死は、或る意味では、素晴らしい死だったかもしれませんね。 ───54歳でしたね。 武満 僕は56歳だ。間もなく57歳。もう駄目だなあ。だが、今さらガタガタしたってはじまらない(笑)。あとはダラダラと駄作を作って、どれだけ長く続くかってことですよ(笑)。 ───50歳を過ぎてから、芸術家としての分岐点はどのへんにあるんですか。 武満 それはやはり生理的な衰えというものがありますからね。感受性だって生理のうちですから、変わるでしょうね。運動の感覚だって鈍るし──。実際、50ぐらいになると、否応なしに“死”を考えますよね。考えないと言えば嘘になります。そういうことで、多少変わるでしょう。開き直りもでてくるでしょうしね。 それにしても、タルコフスキーは、独特な感受性の持ち主でしたね。魔女が出たり、宗教的なにおいがあったり、それで核戦争ですからね(『サクリファイス』)。ふつうだったらバラバラになうそうなものを、あれだけ一つの世界に統合し得る能力というのは考えられないほどのものですね。彼は病みながらも、柔軟性をいつまでも失わずにいられた。 空中に浮遊する場面があったでしょ。あれなんか、古い名画を見ているような荘厳な感じがしてくるものね。映画という、ある限られた時間のなかに、永遠をかい間見せる能力というのは、やはり天才にしか持ちえないものなんでしょうかね。 (たけみつとおる/作曲家) |
|




