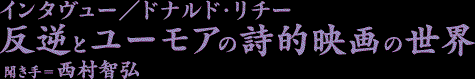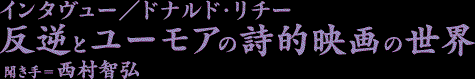|
酔っ払い映写技師と『市民ケーン』
Q. リチーさんは、「黒澤明の映画」や「小津安二郎の美学」といった日本映画の評論、あるいは日本映画を海外へ紹介した業績などがよく知られていると思います。
しかし、リチーさんの活動の幅はじつに広くて、全体像がつかみにくいところがあります。
アメリカ文学の研究者としても実績があり、さらには小説や戯曲を書いたり、演劇の演出をなさっている。
日本文化についても深い造詣があり、
さまざまな伝統文化についての本を書かれています。
歌舞伎や能の脚本や演出も行っていますね。
そのうえに、音楽をやったり、画を描いたり。
リチー 版画もやっています。
Q. 百科全書的な知識と才能です。
その広範な活動のなかでも、映画はひとつの中心をなしている。
ところが、映画作家としての側面は必ずしも知られているとはいえません。
その原因のひとつとして、ここしばらくのあいだリチーさんの作品をまとめて見る機会がほとんどなかったことがあると思います。
今日は、リチーさんの映画作家としての側面を中心にお話をうかがいたいと思います。
どのようにして映画と出会ったのか、またどのようにして映画をつくりはじめたのか、そのあたりからお聞かせください。
リチー ぼくが小さいころ、両親はよくぼくをどこかへ置いて出かけていました。
いちばんよく置いていかれたのは映画館だったのです。
ですから三、四歳のころから映画を見ていました。
沢山の映画に漬ってしまうと、現実のことが現実でなく、映画のほうが現実になる。
現実の世界より映画館のほうが住みやすい場所になっていたんです。
いまでも映画館に入って暗くなると、どこか故郷に帰った気持ちになります。
映画はもうひとつの別の現実なのです。
そして、本当の現実は自由にならないのですが、映画の現実は自分でつくれるということがわかったのです。
16歳の時、オハイオ州にある小さな映画館でのことです。
ぼくはそのころ、映画ならなんでもがむしゃらに見ていました。
その日も、なにをやっているか知らないでその映画館に入ったんです。
そこの映写技師は飲んべえでした。
ぼくは映画を見ながら、今日も映写技師は酔っぱらっているのではないかと思ったんです。
だって、いちばん最初のシーンで男が死んでしまう。
ぼくはそれは最後のリールではないかと思いました。
Q. 酔っぱらってリールをかける順番をまちがえたということですか。
リチー そうです。男が死んだ後に、急にニュースがはじまりました。
ああこれが最初のリールでいいのかと思っていると、今度は過去に戻る。むちゃくちゃじゃないかって。
しかし、しだいにだれも酔っぱらっていないことに気がつきました。それは芸術だったのです。
映画はオーソン・ウェルズの『市民ケーン』。
ぼくは一日中映画館にいて、この映画を三回見ました。
そして家に帰って、親にカメラを買ってくれと頼みました。
Q. 『市民ケーン』を見ることによって、映画をつくることに目覚めたのですか。
リチー あの日、あの映画を見たことが決定的だったのです。
あのとき、ぼくのなかで現実と映画がはじめて一緒になったのです。
父が8ミリカメラを買ってきてくれて、その次の日からカメラを回しました。
日曜日で、小さな村の家で何か撮ろうと思った。
あとになってそれがドキュメンタリーの一種だったとわかったんですが。
つぎに妹を俳優に使ってドラマをつくりました。
こうして8ミリ映画の制作がはじまったのです。
やがて戦争が始まり、戦場にかりだされます。
戦後進駐軍として日本に来ました。
ときどきアメリカに帰ってカメラを回し、まだ現存している8ミリ映画をつくりました。
そのころは、どの作品も何かに影響されたんですね。
『市民ケーン』、ジャン・コクトーの詩人の血、ブニュエルの『アンダルシアの犬』や『黄金時代』、ロバート・フラハティの『ナヌーク(極北の怪異)』などに。
Q. 16ミリ映画をはじめたのはいつのことですか。
リチー 16ミリのカメラを買ったのは大学を卒業してからです。
日本に戻ってきて、16ミリで映画をつくりました。10年ほどですね。
1968年にニューヨーク近代美術館の主事になったんですが、あのころからあまりつくらなくなった。
ときどきはつくりましたよ。テレビの制作で『黒澤明』など。
モノクロは想像力をかりたてる
Q. 多くがモノクロですが。
リチー モノクロでセリフはありません。
本当に現実を表現できるのはモノクロだと思っています。
はっきり、白、黒になっているほうがいい。
コントラストをはっきりさせたほうが、見る人の想像力を働かせることができると思います。
白と黒の間にグレーがあって、グレーを使ったほうが現実に近い。
でも、それでは見る人はただ受けとるだけです。
コントラストをはっきりさせると、見る人が想像してそのあいだをつくらなければならない。
想像を利用すると映画は本当にストロングになるのです。
Q. 固定ショットが多いのはどうしてでしょうか。
リチー 『戦争ごっこ』で気がつきましたが、水平線はいつもおなじところにあります。
カメラに見られるということを逆の立場にしたかった。
カメラに見ないでくれといいたかったんです。
ぼくはあまりカメラを動かしません。
カメラを動かすということは、そこに写っているものを見ろと指示することです。
ぼくは、カメラと写されたもののあいだに何も介在しないことが好きです。
動きのためにカメラを動かすことはありません。
ブレッソンみたいに、小津のように、だんだんストイックになっていきます。
でも、いまつくる機会があったら、カメラを動かすでしょうね。
ぼくはタルコフスキーが好きです。
タルコフスキーのカメラの動きはよくわかるんです。
いつ動くことが必要で、いつ必要でないか。
必要でなければ動かさなくていい。
カメラを動かすのはいちばん簡単なことです。
ぼくはできるだけ簡単な方法で、深いものを表現したい。
コメディだと気づかない
Q. 寓話的な作品も多いですね。
リチー いつもウラから何かを見なければと思っています。
はっきりと意味を言ってしまうのはおもしろくない。
あたりまえすぎます。
実験映画は、ひとつの文章、あるいは詩であると思っています。
けっして小説ではありません。
Q. リチーさんに一貫しているのは、個人的だけれども、
普遍的なものにつながっているような方法をつくりだすことではないでしょうか。
リチー そうです。実験映画は、とても個人的なものだと思います。
そして、できるだけ自分の中の深いところを見せるべきです。
「あなたの映画はぜんぶセックスの映画だ」といわれたことがありますが、個人の核となるいちばん深いところに行きたいわけだから、当然セックスの問題にいきつきます。
それで、ぼくの映画はほとんど喜劇です。
まじめなことを不まじめに、不まじめなことをまじめにすることに興味がある。
ユーモアとは逆を信じることです。
もし普通の撮り方だったら、「ああなるほど」と納得するだけです。
逆にすると「あっ、なんだ」という驚きがあります。
ぼくの映画はTransgression(反逆)とDissidence(不一致)が基本的なテーマです。
Q. 『戦争ごっこ』や『五つの哲学的童話』のように残酷であったり、『シベール』のようにグロテスクであったりしますが、そこにはつねにユーモア、あるいはアイロニーが感じられます。
リチー 『シベール』では、予想もつかないことがありました。
ヨーロッパで見せたとき、みんな怒ったんです。アウシュヴィッツと同じだって。
そんなつもりではなかった。
アウシュヴィッツのことは少しも考えてなかった。
だからドイツでは絶対に見せられない、フランスでも。
イギリスではフィルムが燃やされてしまったんです。
この作品がコメディだということが、だれにもわからなかった。
いまはちがうと思うんですよ。30年も経っていますからね。
ちゃんと理解できる。あの時代はそうではなかった。
『死んだ少年』にまちがいがあるとするなら、コメディーになっていなかったということでしょうね。
もう一度撮ることがあったらコメディーにしたい。
三島(由紀夫)さんはこの映画が好きでした。
この映画の世界は三島さんの趣味ですよ。
愛することと死ぬことというテーマ、あるいは美少年が登場するところとかね。いま見ると自分でも恥ずかしい。
同性愛を扱ったということではなく、そのまじめさがくだらないと思う。
三島さんもやっぱり喜劇が好きでした。
『五つの哲学的童話』の三つ目のエピソード(4人でピクニックに行くが、そのなかのひとりを三人で食べてしまうという話)、あれを何回も見て笑っちゃって、これは傑作だと言ってくれました。
(にしむらともひろ・映画研究者/「イメージフォーラム」誌2000年冬季号より)
|
|

 シベール シベール

死んだ少年
 戦争ごっこ 戦争ごっこ
 熱海ブルース 熱海ブルース
 ふたり ふたり
|