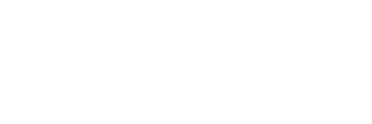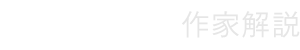スタン・ブラッケージとチャールズ・M・シュルツ(『ピーナッツ』)の霊を、ほぼ同分量チャネリングできる映画作家がいると言ったらどう思うだろうか。彼のアニメーションは、警告もなくお笑いから実存主義へと方向転換する。また彼の手書きの絵は、どんなハリウッド製ファンタジーにも匹敵する特殊効果を生み出す。また彼は、リヒャルト・シュトラウスの弦楽と同時にスカトロ的なユーモアへの趣向を併せ持ち、デジタルカメラを忌避してアンティークの35ミリカメラでアニメーションを撮影する。そして、彼はこの斜陽の映画業界で幾人ものファンがその作品を見るために列をなすような作家である。そんな作家と言えば、ドン・ハーツフェルト以外に誰がいるであろうか。
このアニメーション作家は、非常にシンプルな技法を使いながら、観るものを遠い銀河の果てへと吹き飛ばし、我々が最も古くから抱いている不安を綿密に辿り、お話のオチのメカニズムを破壊する。ハーツフェルトの短編一本に、数本の長編映画分に値する華麗なナンセンスと想像力の広がりが詰まっている。
その濃密さは、彼の手書きへのこだわりによるところが大きい。技術的にも精神的にも、ハーツフェルトの『ああ、アムール』や『ビリーの風船』といった棒状のキャラが喚く初期の作品から、心を打ちのめすような才気にあふれた傑作『人生の意味』や「きっとすべて大丈夫」のシリーズへの変化は驚く程深い。
別の可能性もあり得ただろう。21歳の時、ハーツフェルトは四本目の短編『ビリーの風船』をサンタバーバラ校で有望な映画学生として完成させ、カンヌ映画祭のコンペ部門に入選した。グランプリを受賞する事はできなかったが、彼のエッジの効いたウィットは観客の胸を打ち、台詞を一語一句憶えたり、登場キャラクターを自分の体にタトゥーとして彫ってしまう人も現われた。このような人気の広がりを夢見るマーケティング担当者たちは、ハーツフェルトが、そうした企業の商業主義を標的にした次作『リジェクテッド』を制作した後も、彼に広告のオファーをし続けた。それに乗って収益を得る代わりに、ハーツフェルトは、1作品2年という制作サイクルに入り、未知の世界へ足を踏み入れる事を選んだ。彼自身が自分のオンライン日記で言っている:“悪いけど、森の中を歩いたりして、自分の世界を探索する方がいい。”
ハーツフェルトの労力に満ちた制作過程には必ずリスクが伴う。彼の複雑なアニメーションは、ビデオ機器の巻き戻しの恩恵を受けずに何十回と同じフィルム片に作業を施す。それは彼の作品のストーリーボードが、物理学の実証に近づくことであり、予期せぬ偶然の発見が生じることに対して常に開かれているという事でもある。ハーツフェルトの制作方法自体が既に強迫神経症的なのだ(彼の『ああ、ラムール!』では「僕の親友カフェイン」にクレジットが捧げられている)。完成作品に起きる奇跡は、何千時間もの作業を裏切るような、自然発生的な輝きを取り込んでいるからでもあるのだ。
ハーツフェルトのおかしさの感覚は、夢や記憶違い、よくあるような誤解、言葉に出されない観察、日々に漂うがらくたなどと直接的な関わりを持っている。今になって彼の初期の短編を観てみると、一見ぞんざいに描かれたキャラクターが、いかに表現のニュアンスを生み出しているかということに即座に驚かされる。彼は、脚本家として初めから非凡な鋭敏さをみせていた。例えば『リリーとジム』では、いくつかの会話の間だけで笑いを誘い、お見合いデートの困難さを抽出してみせた。初期のこうしたスケッチから、アニメーションにおける深遠さまで至るのは、ハーツフェルトにとってほんの2、3の跳躍に過ぎなかったのだ。そのステップとなったのは「2001年宇宙の旅」へのオマージュ、『人生の意味』である。
この作品では、ハーツフェルト独自の視点で西洋文明の衰退が描かれる。孤立主義者たちが、狂ったように束になって同じ言葉を呟き続け、さながら不協和音の戦争の様相を来すさまは、ゴヤかナサニエル・ウエストの漫画版のようである。それは、未来の宇宙についての畏敬に満ちた予言であり、息を飲むような数分間で、ハーツフェルトは自分自身の想像力の限界に挑戦している。
『きっとすべて大丈夫』シリーズでは、ハーツフェルトの切れ目のないナレーションが、映像の勢いに追いついて来る。作品の中心に癲癇持ちの棒線画キャラクター、ビルを据え、彼が世界を理解しようとして世界から遊離していく様が描かれる。これらの作品の複数のパネルのような画面構成は、壮大な宇宙について語ろうとはしているが、キャラクターが受ける試練の人間くささを損なう事はない。このシリーズ2作目で、ハーツフェルトの現時点における最高傑作『あなたは私の誇り』では特に、作家による意図的かつ怒りに満ちた物語の脱線は、まぎれもなくジョイス的な嗜好が見て取れる。作品を見続けていると、最初はランダムにみえる挿話も、実際にはビルというキャラクターの解離性障害が織りなす錯綜して断片化したモザイクを形作っていることが分かってくる。怒濤の省略や虫食い穴が、形式に強烈な揺さぶりをかけ、ハーツフェルトの熱狂的なファンでさえ圧倒されて笑う事もできないのである。
マックス・ゴールドバーグ(サンフランシスコ・ベイ・ガーディアン映画批評家)