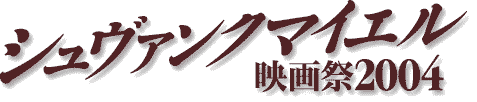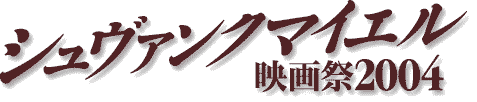|
 プロ(計90分) プロ(計90分) |
|
|
|
|
自然の歴史(組曲)
1967年/9分/カラー/クロムニェジーシュ映画祭、オーバーハウゼン映画祭受賞
◎巻き貝から爬虫類、鳥類を経て人類に至るめくるめく博物誌。
|
 |
|
|
|
|
部屋
1968年/13分/モノクロ/映画祭、ブリュッセル映画祭、オーバーハウゼン映画祭受賞
◎部屋の中の哀れな男。壁穴を覗くと殴られ、椅子に座ると、椅子は逃げ出す。
|
 |
|
|
|
|
対話の可能性
1982年/12分/カラー/ベルリン映画祭、アヌシー映画祭、メルボルン映画祭、シドニー映画祭受賞
◎対話の形をシュールに描いた傑作。「永遠の対話」「情熱的な対話」「不毛な対話」の三部構成。
|
 |
|
|
|
|
地下室の怪
1982年/15分/カラー/オーバーハウゼン映画祭受賞
◎地下室にひとり降りてゆく少女。逃げ去るジャガ芋など奇怪な出来事に少女の恐怖は極限に…。
|
 |
|
|
|
|
陥し穴と振り子
1983年/15分/モノクロ
◎拘束された主人公を今にも八つ裂きにせんとする巨大な殺人機械の数々。
|
 |
|
|
|
|
男のゲーム
1988年/15分/カラー
◎熱狂的なサッカー観戦。選手の頭に列車が飛び込み、選手が次々にミンチにされてゆく。
|
 |
|
|
|
|
セルフポートレート
1988年/2分/カラー |
 |
|
|
|
|
闇・光・闇
1989年/8分/カラー/ベルリン映画祭、クラクフ映画祭、ザグレブ映画祭受賞
◎灯がともされ、小さな部屋の中の目玉の付いた手から始まる不思議な出来事
|
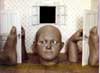 |
|
 |
|
|
 プロ(計89分) プロ(計89分) |
|
|
|
|
棺の家
1966年/10分/カラー/マンハイム、クロムニェジーシュ映画祭受賞
◎道化たちがお互いに木槌で殴り合うスラプスティック・コメディ。
|
 |
|
|
|
|
エトセトラ
1966年/7分/カラー/カルロヴィ・ヴァリ映画祭、オーバーハウゼン映画祭受賞
◎フロッタージュの技法を使い、「翼」「鞭」[家]のエピソードで構成された作品。
|
 |
|
|
|
|
ドン・ファン
1970年/33分/カラー/クロムニェジーシュ映画祭受賞
◎後の長編『ファウスト』を思わせる、放蕩息子であるドン・ファン復讐譚。
|
 |
|
|
|
|
コストニツェ
1970年/10分/モノクロ
◎15世紀のフス戦争の死者など数万人の納骨堂に関するドキュメンタリー的作品。
|
 |
|
|
|
|
レオナルドの日記
1972年/12分/カラー
◎レオナルド・ダ・ヴィンチの日記からのデッサンや図面が動き出す。
|
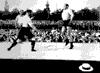 |
|
|
|
|
アッシャー家の崩壊
1980年/16分/モノクロ/クラクフ映画祭、ポルト・ファンタジー映画祭受賞
◎「全ての無機物にも知覚はある」。アッシャー邸とその精神が崩壊してゆく。
|
 |
|
 |
|
|
 プロ(計91分) プロ(計91分)
|
|
|
|
|
シュヴァルツェヴァルト氏とエドガル氏の最後のトリック
1964年/12分/カラー/ベルガモ映画祭、マンハイム映画祭、トゥール映画祭受賞
◎ラテルナ・マギカ演出経験を生かしたシュヴァンクマイエルのデビュー作。
|
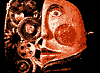 |
|
|
|
|
J.S.バッハ--G線上の幻想
1965年/10分/モノクロ/カンヌ映画祭受賞
◎ひび割れた壁や風にさらされた窓などがバッハの曲とともに動き出す即興的な作品。
|
 |
|
|
|
|
庭園
1968年/17分/モノクロ/ヴェネツィア映画祭受賞
◎郊外の友人の家に招かれると手をつないだ人々が生け垣のように家を取り囲んでいた。
|
 |
|
|
|
|
家での静かな一週間
1969年/20分/カラー&モノクロ/オーバーハウゼン映画祭、タンペレ映画祭受賞
◎ドアから部屋を覗くと、日常的な物が勝手に動く超現実的な世界がそこにはあった。
|
 |
|
|
|
|
ジャバウォッキー
1971年/14分/カラー/映画祭、アトランタ映画祭受賞
◎「鏡の国のアリス」の怪物ジャバウォッキーの詩が朗読され、おもちゃが動き始める。
|
 |
|
|
|
|
オトラントの城
1973〜79年/18分/カラー&モノクロ
◎幻想小説『オトラント城綺譚』の舞台が、実は東ボヘミアに実在するという。
|
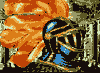 |
|
|
|
|
      プロの紹介 プロの紹介 |
|
|
|